筆者は民間企業の会社員ですが、毎年会社から技術士二次試験を受けることを推奨されています。
しかし、合格率10%前後の難関資格ですので、相応の時間と労力を割かねば先ず合格は見込めないでしょう。
また、学生とは違い受験は任意となりますので、モチベーションや目的意識の設定・維持も重要になります。
ここでは技術士試験の良い点と悪い点について整理します。
良い点
- 技術士は国内のみならず国際的に権威のある資格なので、国内外で評価される
- 試験勉強をすることで専門分野の知識が広がる・深まる、記述能力が高まる
- 会社によっては一時金やベースアップがある
- 官公庁の事業で技術士が必須となる業務を受注することができる
悪い点
- 十分な試験勉強の時間と労力が必要、試験時間も長い(筆記試験でまる一日、口頭試験で半日)
- TOEIC等とは違い、落ちたら結果は不合格のみ(A~Cの判定は出る)
- 試験が年に一回のみ、人によっては仕事とプライベートの予定調整が必要
良い点の解説
国内外の評価
国内における技術士の評価は、民間企業では高いと感じます。
名刺交換の際に技術士と記載されていると、それだけで一定の信頼が得られます。
ただし、大学や研究機関では博士のみを取得している人が多く、そのような環境では技術士資格はそれほど重要視されていないように感じます。
また、技術士は国際資格なので、名刺に英語で書くことができます。
筆者の経験したアジアの国では技術士を取得している人を見かけたことはありませんが、先進国では取得している人が多いのかも知れません。
専門分野の知識が広がる
筆者は調査会社に所属していますが、専門分野と言えど出題範囲は広いと感じます。
ゼネコンなどに所属している方は日頃からある程度かじっている出題範囲かも知れません。
専門分野の知識が広がることで、異動や転職、学会や学際的な討論に強くなります。
単純に知識欲も満たされます。
記述能力が高まる
専門分野の表現については報告書や報告会で行うと思いますが、報告書や報告会はある程度テンプレート化してしまっているかも知れません。
技術士試験では問題に合わせて回答しなければならないため、より柔軟な表現能力が求められます。
一時金やベースアップがある
一時金の金額は会社によって差が大きく、10~50万円の会社が多いようです。
一時金受領後に一年以内に転職すると返済義務が発生する場合もあります。
ベースアップは0~3万円の会社が多いようです。
ベースアップは長く勤続するほど合計金額が多くなるので、転職予定が無い方に向いています。
技術士が必須となる業務を受注することができる
官公庁の事業では技術士の在籍が仕様で定められている場合があり、技術士は会社から重宝されます。
技術士資格を取得することで重要な事業に携わる機会が増え、昇進・昇給に繋がると考えられます。
筆者の会社では部長以上の役職の方は皆、技術士資格を取得していました。
悪い点の解説
時間と労力が必要
自身の専門分野を選択したとしても出題範囲は広く、十分な試験勉強が必要となります。
また、技術士試験は過去に記述式→マークシート式→記述式と変遷しており、現在は記述式になります。
記述式はマークシート式に比べて試験勉強がしにくいと感じる方は多いと思います。
答案を添削してくれる勉強会もあるようですが、受講料が数万円と高額だった記憶があります。
落ちたら結果は不合格のみ
TOEICなどでは目標点に到達しなくても点数として結果が残りますが、技術士試験は落ちたら不合格という結果しか残りません。
ただし、問題I,II,III毎にA~Cの判定×3が試験結果のハガキに記載されています。
筆記試験を合格して口頭試験で落ちた場合、来年はまた筆記試験からやり直しになります。
また、受験2回目以降は前回の受験票を提出することで、受験手続が若干簡略化できます。
試験が年に1回のみ
TOEICなどのポピュラーな試験は年に複数回実施されますが、技術士試験は年に1回しか受けられません。
また、筆記試験に合格した後の別日に口頭試験があるので、年2日のスケジュール調整が必要になります。
夏場に野外での作業が多い業種では筆記試験のスケジュール調整が難しいので、早い時期から会社のスケジュールに明記したり上司に連絡したりすると良いでしょう。
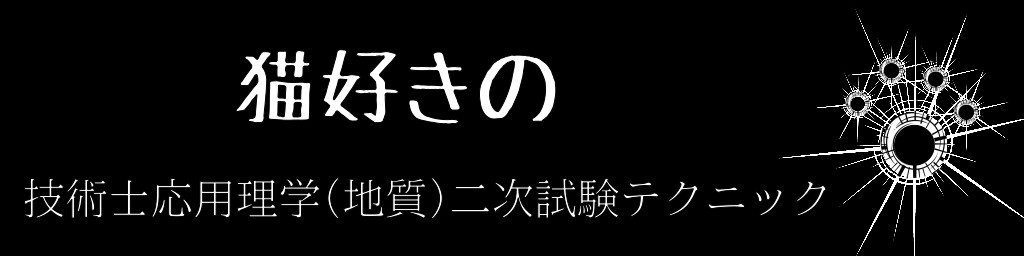

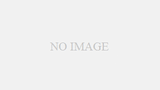
コメント